誠ブログは2015年4月6日に「オルタナティブ・ブログ」になりました。
各ブロガーの新規エントリーは「オルタナティブ・ブログ」でご覧ください。
書評:『アラブ500年史(上下):オスマン帝国支配から「アラブ革命」まで』
ライフネット生命会長兼CEO 出口治明の「旅と書評」
書評:『アラブ500年史(上下):オスマン帝国支配から「アラブ革命」まで』
ライフネット生命保険 代表取締役会長兼CEO。1948年三重県生まれ。京都大学を卒業。1972年に日本生命に入社、2006年にネットライフ企画株式会社設立。2008年に生命保険業免許を取得、ライフネット生命保険株式会社に社名を変更。
当ブログ「ライフネット生命会長兼CEO 出口治明の「旅と書評」」は、2015年4月6日から新しいURL「http://blogs.itmedia.co.jp/deguchiharuaki/」 に移動しました。引き続きご愛読ください。
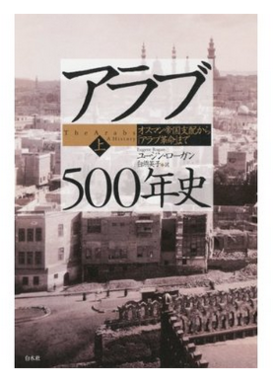 『アラブ500年史(上下):オスマン帝国支配から「アラブ革命」まで』
『アラブ500年史(上下):オスマン帝国支配から「アラブ革命」まで』
ユージン ローガン(著)、白須 英子(翻訳)
ムハンマドからウマイヤ朝、アッバース朝などの盛期に至るアラブの歴史は、わが国でも比較的よく知られている、と言っていいだろう。僕たちがいつも戸惑うのは、あの輝かしいイスラーム帝国の時代と、現代のアラブ社会の混迷振りとの著しい落差にある。その間隙を埋める意欲作が現れた。それが、本書である。本書は、1516年のマルジュ・ダービク(アレッポ郊外)の戦いから筆を起こす。エジプトのマムルーク朝とオスマン朝が対峙した。勝利したオスマン朝のセリム1世は、エジプトを手に入れた。この時点から、アラブ世界はイスタンブールの支配を受けることになる。
本書は上下2巻から成る。上巻はオスマン朝の400年に及ぶ支配下のアラブ世界を描き出し、第1次世界大戦後の英仏の支配から、第2次世界大戦終結時までを取り扱う。下巻は、ナセルに象徴されるアラブ・ナショナリズムの台頭からその衰退、石油の時代を経て、冷戦崩壊後の現代(アラブの春から1年)までを叙述する。パレスチナ問題のみならず、僕たちには馴染の薄いレバノンやシリア、ヨルダンの状況が丁寧に活写されていることが、特徴的である。そもそも中東の混迷は、パレスチナのみならず、周辺諸国の状況をきちんと踏まえなければ理解できない性質のものなのだ。
豊かなエジプトを250年にわたって支配してきたマムルークは、対オスマン戦で絶滅した訳では全くなかった。遠いイスタンブールの支配者は、シリアであれエジプトであれ、現地人の有力者に現地の行政をある程度、委ねざるを得なかった。マムルークを絶滅したのは、19世紀に入って「エジプト帝国」を樹立したアルバニア人、ムハンマド・アリーである。アリーは、いわば「和魂洋才」でエジプトを近代化し、衰退するオスマン朝に1つの手本を提示した。アラビア半島に生まれた「原理主義」ワッハーブ派を退治したのもアリーである。オスマン朝は、英仏露のパワーバランスのおかげで領土が保全され、第1次世界大戦まで生き延びる。しかし、北アフリカは英仏によって植民地化された。例えば、アルジェリアは、太守がフランス領事をハエ叩きのようなもので叩いたことが植民地化のきっかけとなった。「高貴なアラブ人、サラディンのような人物」アブドゥルカーディルの奮戦も空しく、アルジェリアはフランス領となる。第1次世界大戦で、英国は三枚舌を使う。「フサイン=マクマホン書簡」では、大シリア圏をアラブ王国(ハーシム家)に与え、「サイクス=ピコ協定」では、大シリア圏をフランスに、「バルフォア宣言」ではパレスチナ(大シリア圏に含まれる)にユダヤ人国家を、それぞれ約束したのである。ここに争いの種が蒔かれた。誠に大国の思惑ほど傍迷惑なものはない。第1次世界大戦後、アラブ世界はウィルソン大統領の14カ条(民族自決)に夢をつなぐが、ウィルソンの理想主義は、英仏の現実主義の前にあっさりと敗退し、サイクス=ピコ協定の線に従って、中東は英仏により分割された。ハーシム家には、代わりにヨルダンとイラクが与えられた。著者は、克明な日記を残したダマスカスの床屋、アフマド・ブダイリ、アリーによってフランスに派遣されたムスリム宗教学者リファーア・タフターウィー、エジプトの女性リーダー、フダ・シャーラウィなど、それぞれの時代を代表する個性豊かな人物の目を通して、アラブの400年を描き切るのである。
下巻は、ナセル革命から始まる。アリーの王朝は、ナセルによって終止符を打たれた。アラブ世界はナセルに熱狂するが、アラブ諸国はイスラエルとの「6日戦争」に完敗する。1967年、アラブのハルツーム・サミットは「3つのノー」(ユダヤ人国家の承認、イスラエルとの交渉、イスラエルとの和平、全てにノー)を採択し、強硬路線に転じた。10月戦争で善戦し、石油戦略を初めて戦争に活用した(ナセルの後継者)サダトによって、1979年、中東平和条約が結ばれ、エジプトとイスラエルの関係は安定に向かう。しかし、パレスチナ問題は置き去りにされたままだった。1982年には身の毛もよだつサブラ・シャティーラのパレスチナ難民キャンプの虐殺事件がおこる。一方、1979年、ソ連がアフガニスタンに介入し、10年に及ぶアフガニスタン紛争が始まっていた。パレスチナに生まれたアブドゥッラー・アッザムは、アフガニスタンを対イスラエル戦争の「訓練地」になると考え、パキスタンに向かう。ビン・ラディンはその門下生であった。1993年、イスラエルとパレスチナ(PLO)は、ようやくオスロ合意にこぎつける。一瞬、和平が近づいたかに見えたが、立役者ラビン首相(イスラエル)の暗殺で、暗雲が漂い、現在に至っているのである。この間に、イラン・イラク戦争があり、イラクのクウェート侵攻があり、湾岸戦争があって、9.11の後、アメリカ軍がイラクに侵攻した。そして、アラブの春とその後の混乱。アラブ世界にとって、第2次世界大戦後の70年は、まさに激動の時代だったのだ。
著者は断言する。「今日のアラブ世界で自由かつ公正な選挙が行われれば、イスラーム主義者がきっと楽勝すると思う」と。加えて、「イランをモデルにしたイスラーム共和国へと進むのではないか」という「欧米の不安には根拠がないように思われる」と。イスラーム主義者は、「正直で腐敗していない政権」に向かうというのが著者の見立てである。泥沼の感がするシリアについて、興味深いコメントがあった。「シリアは統治の難しい国」「シリア人の50%が自分を国家の指導者であると考え、25%が自分が預言者だと思い、10%は自分が神だと思い込んでいるからだ」。これは、ナセルがシリアを合併する前に、当時のシリア大統領クーワトリーが警告した言葉だそうだ。歴史を見なければ、今日のアラブ世界はわからない、その意味でも、中東情勢に興味のある人には、ぜひとも読んでほしい1冊だ。

